その日の執務を終えたリュミエールは、私邸へ戻るために聖殿を後にした。夕刻の風は肌に心地よく、このまま真直ぐに帰るのがもったいないような気がして、庭園を少し歩いてみようかと考えた。女王試験が始まって1カ月余り。少しずつではあるが、新しい宇宙は着実に惑星の数を増やし、試験は順調に行われている。
「これも3人の教官方の指導が的確だからなのでしょうね」
つぶやいたリュミエールの瞳に陰りが走った。それは普段から穏やかな微笑みを絶やさぬ、水の守護聖の表情を損なうものではなかった。しかし、その瞳の奥にはやりきれないような悲しみが宿っている。沈む心を抱えたまま、目的もなく庭園を歩いていたリュミエールは、カフェテラスで談笑する人々の楽しそうな声に、ふと足を止めた。頬を染めながら語り合う恋人たち。そして少し離れたテーブルで楽しげに話し合う二人が目に入った瞬間、彼は自分の心が沈み込んでいる理由を理解した。
「リュミエール様、こんにちは。お散歩ですか?」
チャコールグレーの髪の少年が笑いかける。その屈託のない笑顔がリュミエールの心を締めつける。
「今日は良い天気ですな。昼間は少しばかり暑いくらいでしたが、この時間ともなると涼しい風が吹いて、実に気持ちがいい。それでティムカと散歩に出たというわけです。」
「そうなのですか。私も何だかまっすぐに館に帰る気になれなくて、あなた方と同じように散歩でもと考えたのです。」
「本当ですか? なんて素敵な偶然なんでしょう」
「リュミエール様、どうです。一緒にお茶でも」
「ありがとうございます、ヴィクトール。せっかくですが、私はご遠慮させていただきます。遅くなることを館の者に伝えていないので、心配をかけてしまうかもしれませんので」
「そうですか……。でも今度きっと、ご一緒してくださいね」
「ええ、次の機会にはきっと……」
リュミエールは努めて穏やかに、そして平静を保ちながら二人に告げた。
「それでは、また明日、お会いしましょう」
ともすると早まりそうになる歩調を乱さないよう、リュミエールはその場から遠ざかった。カフェテラスで談笑する二人からは見とがめられない場所まで来ると、彼は振り向いた。ヴィクトールは穏やかな瞳でティムカを見守っている。弱冠13歳で女王候補に教鞭を執るという重責を負っているティムカは、非常に真面目な性格のため、また慣れない聖地での生活のため、常に緊張しているようだ。けれど職務を離れ、ヴィクトールと一緒にいる時だけは年齢相応の表情を見せる。それだけヴィクトールに信頼を寄せているのだろう。そんな二人を微笑ましく感じる一方、抑え難い暗い感情が胸にこみ上げるのだった。
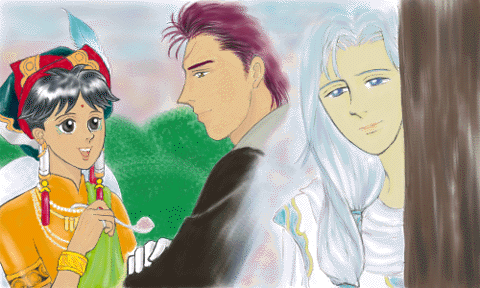
ヴィクトールは彼の率いる部隊の死を賭しての活躍により、幾多の民を彼等の住む惑星を襲った災害から守った。一般市民の生命の安全の確保を最優先としたため、王立派遣軍は多くの兵士を失った。しかし、それを補って余りある功績により、ヴィクトールは将軍位を得、「悲劇の英雄」として、歴史や人々の記憶にその名を残すことになる。彼の活躍は聖地にも伝わっていた。リュミエールは女王試験に協力するためにここを訪れたヴィクトールと初めて言葉を交した時、その心の奥深くに存在する悲しみや後悔を感じ取った。しかし彼は、努めてそういった感情を押し殺し、誰に対しても好意的に、快活に振る舞う。リュミエールはヴィクトールの強くやさしい心に好意を抱くと同時に、その傷ついた心を何とかして慰めたいと思うようになった。やさしさを司る水の守護聖の気持ちがヴィクトールにも、気持ちが伝わったのだろう。時を置かず二人は親しくなり、お互いの執務室を訪問し合うようになった。リュミエールの部屋にいる時はハーブティーを、ヴィクトールの部屋では薄く煎れたコーヒーを飲みながら、とりとめのない話をするだけの関係。時々ヴィクトールは苦い過去の出来事を口にすることがある。苦しい思い出は言葉にすることで、誰かに聞いてもらうことで、その重みを軽くするものだと知っているリュミエールは、静かにヴィクトールの言葉に耳を傾けるのだった。
「私は少し、思い上がっていたのかもしれませんね」
自嘲ぎみにつぶやき、リュミエールは足早に館へ戻った。ヴィクトールの悲しみを癒すことができるのは、自分だけだと、いつの間にか思い込んでいたリュミエールは、知らず知らずのうちにティムカに向けてしまった嫉妬心に気付き、そんな醜い感情を抱いている自分自身を嫌悪した。
「あの純粋なティムカに、嫉妬するなんて……。私はなんと心の狭い人間なのでしょう。」