「土の構造」
〜第70回つくば有機セミナー報告〜
開催日 1998年 9月26日 報告者 橘 泰憲(筑波大学)
1990年に第一回が開催されたつくば有機セミナーも、とうとう70回を迎えた。70回の間にさまざまな方々が参加された。通算約3000名。しかし、どうしても報告者からの一方通行となりがちだったことから、第67回からは「向上性」「双方向性」を目指し、有機セミナーを定員50名とする申込制となった。
産業革命以来、少しずつ知らない間にできていた世界の歪みが音をたてて崩れようとしているいま、私達に必要なのは何なのか、このセミナーで幅広い勉強をしてきた。ここで大切なことは、知識の集積、いい話、ではなく「自分がどれだけ変わったか」「何をするか、何をしようとしているか」。そしてこれが現在筑波大学で開講されている「有機農業論」の始まりともなった。
「有機農業論」も、今年度で3年目を迎え、最初は無関心だった学生もほんの少しずつであるが手応えが感じられるようになったという。
「有機農業って常識でしょう?」
と言う大学院の授業での学生の言葉に橘先生は大いに勇気づけられたそうだ。”エンカレッジ””エンパワーメント”。学問とは人間を根本からはげますものであり教育は、誰もが持っている「何かを成し遂げる力」をコミュニケーションを通じて引き出すものである。
このような前置きの後、今回のセミナーは、今年の春、無農薬のブドウ栽培を確立された小林寳治さんを迎え開催された第67回有機セミナー「土の団粒構造」の解説をかねて行われた。
第67回有機セミナーでの小林さんのお話しは、普段、農業、とりわけ土に接していない私達には大変難しい内容だった。おまけに、聞きなれない東北訛の口調は、ただでさえ難しい話しをますます難しいものにしてしまった。セミナー参加者からの要望もあり、今回橘先生がもう少し、かみ砕いて説明することになった。
小林寳治さんは農業を始めて67年になる。20年前からすでにブドウの無農薬栽培を確立していた。食べるときかならず皮を口に含むことになるブドウにとってこの無農薬栽培の技術は画期的なものであるはずだ。にもかかわらず、20年経った現在でもこの農法は社会にまったく認知されていない。
世間のあまりの認識の浅さに小林さんがあきらめ切っていた矢先、「筑波大学でタチバナという奴が有機農業をやっているらしい」という噂を聞き、「そんな筈はない」と、半信半疑で橘先生のもとを訪ねて来られたそうだ。有機農業が取り持った不思議な縁。しかし、”大学で有機農業をやっている”ということが遠く、東北の農業者の話題にまで昇るほど、大学では有機農業はまったく無視されている事の裏返しとも言える。 橘先生は言う「日本の大学にいる農業研究者約1万人は、役立たずで、まったくもって無駄、それはひどいものだ」「わたしが大学で有機農業の授業を実践していること自体が奇蹟」だと。
大学がこのような有様なのだから、学会とはまったく別のところで行われている小林さんの粘土農法が広まらないのもこの日本の体制においては何ら不思議なことではないのかもしれない。
小林さんが実践されている農業は大学での農業とはまったく反対の方法で行われている。大学で通常行われているのは「理論」がまず先にありそれから「現象」を導いていく。小林さんがその反対だというのは、小林さんの場合、まず「現象」があるということだ。そして「現象」から「理論」を導き出している。そのため、小林さんのなかでは十分な説明がついている。言うことすべてが明快で、自身に満ちている。「〜のはずだ」「〜とおもわれる」ではなく、どんな質問にでも即答できる。
だが、それが、あまりに「小林流」であるが故に、従来の農学研究では説明できない。これが、私達のような土になれ親しんでいない”農業ど素人”に難しく感じられる大きな理由である。
小林さんは、ご自身の農場に粘土を入れ、農薬なしではなり立たないといわれているブドウ栽培の無農薬化を成功させた。ところが、始めの7年間は収穫はまったくなし。普通の人ならばここであきらめてしまいそうだが、周囲からの強い援助、励ましもあり何とか乗り越えられた。その常人では計り知れない苦労から導き出したのが、現在も実践されている「粘土農法」である。
粘土農法で最も重要なことは「土は生きている」ということ。農産物、畜産物ですら商品としか見られないこのご時勢では「つち」が生き物として扱われるということはあまりない。20年前ならなおさらだっただろう。橘先生や、小林さんが嘆くのは、大学の研究室において、頭では「土はいきもの」であることを知っていながら、その扱いはまるで勘違いしているということだ。
大学の研究室で、土は生きていることはない。なぜなら、分析するときはいつでも土を乾かしてしまう。どんな生き物でも乾かせば死んでしまう。そして、生きていない土をまた加水分解して変化させ、一生懸命分析して「ああでもない、こうでもない」と、ケンケンガクガクやっているのである。そこにあるのは窒素、リン、カリウム(N、P、K)であって、土ではない。
生きた土は粘土であり、さまざまなミネラルを含む。そしてなにより、生きている土は腐植化する。(乾かしてしまうと腐植の実体は捉えられなくなってしまう)この腐植化した土が農業に最も適した団粒構造をつくる。団粒構造をつくるうえで大きな役割をはたす粘土は2ミクロン(0、002mm)以下の粒子となっている。目に見える大きさではない。それが集まってミクロ団粒(十数ミクロン)となり、またそれが集まってマクロ団粒を形成する。ここまで来るとやっと目に見える大きさになる。さまざまな大きさの粘土、ミクロ団粒、マクロ団粒が複雑に組み合わされて土の団粒構造を構成する。
これは、小林さんの「現象」に対して、橘先生が補足として使われた言葉である。ここからの内容は、橘先生がわかりやすく解説し直したとはいえ、化学の知識がある程度ないと理解するのがかなり難しいものだったので、そのなかから理解しやすいと思われるトピックスを選んでみることにする。
すべての物質は原子からなりたっている。原子がさまざまに結合して分子となり、高分子となり、私達の身体を構成する元となる。つまり、私達の身体は原子からできている。
原子は、中心にあるプラスの電気を帯びた原子核と、そのまわりを回るマイナスの電気を帯びた電子で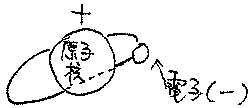 構成されている。「生命現象はすべて電気的現象に還元できる」というのはそういったところから来ている。
プラスとマイナスの電気は決してつりあうことはない。つりあうということは、変化しないもの、永久不変のものということと同じだ。よって、生物を含むすべての物質には絶えず電気が流れている。
構成されている。「生命現象はすべて電気的現象に還元できる」というのはそういったところから来ている。
プラスとマイナスの電気は決してつりあうことはない。つりあうということは、変化しないもの、永久不変のものということと同じだ。よって、生物を含むすべての物質には絶えず電気が流れている。
そんなわけで、地表にも電気は流れている。それを電流という。粘土はコロイドと呼ばれる電気を帯びた粒子なのである。小林さんが気がついたのは、コロイドの電流がつりあう点、「等電点」があるということだ。土壌コロイドの電気が安定している状態では、PHもその土壌の最適PHを示す。
当り前のことだが、土の等電点や最適PHの値は土地ごとに特有の値がある。その値は「ケイバン比」(ケイ=カリウムイオン、バン=アルミニウムイオン)を測ることで知ることができる。
つくばのある関東ロームでは、土壌中にバンの比率が高いので最適PHが6.5。小林さんが住んでいる東北地方では、バンの比率は関東ロームに比べ低いので最適PHは4.5、と地方地方でまったく違う値がある。(わかりやすく言うと東北地方の土壌は関東よりも酸性が強い)
ところが、日本の農業は国の農業試験場が発行する指導書に沿って行われている。もちろん基準は農業試験場のある場所(主に関東地方)。東北地方であってもお構いなく、関東と同じやり方をしろといってくる。
小林さんはその矛盾に気付き、自分自身で研究を重ね、東北地方に最も適した農業を確立した。最適PHが4.5であることを発見したのもこの研究の成果である。
現行農法が行われている土は多くの場合ミネラルが不足している。それは土の構造に片寄りがあるため、ミネラルが流れ出てしまうからだ。それを止めるために、
団粒構造が必要となってくる。
団粒構造を作るにはさまざまな方法がある。小林さんの粘土農法も「絶対」といったものではなく、そのなかの一つだということは確認しておきたい。
小林寳治さんの理論は高校で習う以上の化学の知識がなければなかなか理解しずらい。小林さんが凄いのは、小学校までの学歴でありながら、自学自習でこれほどの理論を導き出したというところだ。はたして、現在、それほどに情熱を持って学んでいる学生がいるだろうか。学生ばかりではない。大学の教授と呼ばれる人々でさえ研究と銘打って目的も目標もない実験、調査を繰り返してはいないだろうか。
小林さんのお話しは、それ自体大変興味を引かれるものだった。だが、それ以上に「農業を続けている小林さん」という存在が、今私達が見落としそうな何かに気がつかせてくれたのではないだろうか。
小林さんの農法には「硫安(硫酸アンモニウム)を使う」といった一見危険極まりないやり方がある。しかし、その理由と土の構造を結び付けて説明されると”なるほどなあ”と納得させられてしまう。いまは、硫酸アンモニウムを使用することはできないのでそれに代わるものを使うが。
とにかく、報告を作るのは大変な労力を要した。「硫安」一つにしても、私達はそれが毒か薬か最初はわかっていなかったのだから。農業に従事している人のあいだではそんな化学式の理論が常識となっていることに驚きを覚えた。大学でなんだかんだ言っていても結局「現場」の人が一番物事を知っているんじゃないか。ということを再確認した。それは、農業ならずともどんな事にも通じる当り前のことだった。つい忘れて知ったかぶった発言をしてしまうことも多いけれど。
荒川陽子