翌日からランディは、仕事の合間を縫ってオスカーの行動を観察するようになった。オスカーがデートの相手にささやく言葉を可能な限り革の手帳に書き留め、その行動を彼なりに詳しく記し、店を閉めてから一人、耳にするだけで赤面するようなオスカーのセリフを自然に口にできるように、そして『いい人』という汚名を返上するための行動を特訓するのだった。同時に複数のことができないランディは、仕事中もセリフの練習などをするものだから、彼をよく知る人々にとって、その行動は実に奇異なものに映った。しかし周囲の様子など眼中にないランディは、連日オスカーの後をつけまわすのだった。その姿は多くの人に目撃され、やがて街に一つの噂が流れた。女たらしのオスカーがとうとう女性だけでは物足りなくなってしまい、いたいけなランディにまで手を出した。純情なランディはオスカーの毒牙に落ちてしまい、オスカーが他の男に手を出さないように見張るようになってしまった。生来の女好きという病気を治すことはできないので、女性とつき合うことは黙認できても、自分以外の男とつき合うことは、尽くすタイプのランディには我慢できないことだったらしいというものだ。
「何が悲しくて、熱血青春坊やに手を出さなくちゃならないんだ?」噂話を聞かされたオスカーは、余りのショックに思わず大きな声をあげてしまった。オスカーの様子を見て楽しそうに笑う美女に彼は言った。
「レディ。君の笑顔はこの上なく魅力的だが、炎のオスカーの不名誉な噂で楽しそうにするのは、勘弁してくれないか? 俺は世界中の女性のナイトになることはできても、むさ苦しい野郎を守ろうなんて考えは、これっぽっちも持ち合わせてはいないんだ。ん? まだ笑っているのか。そんなに意地悪な唇は、この俺が塞ぐしかないようだな……」
余裕たっぷりの様子で美女に口づけようとしたオスカーは、嫌な視線を感じてふと窓を見た。そこにはたった今、話題に上ったランディの顔があった。オスカーと目が合ったランディは慌ててその場を離れようとしたが、乱暴に襟首を掴まれてしまった。
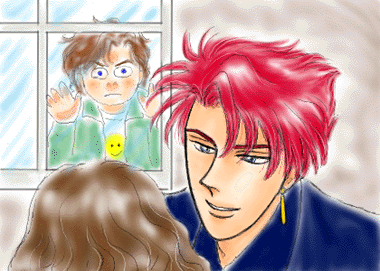
「坊や……何の恨みがあって、この俺の身辺を嗅ぎ回るんだ? 返答次第によっては勘弁しないぜ……」
愛想の良い普段の態度からは考えられない目つきと、凄みを帯びた低い声を聞いたランディは逃げることはもはや不可能だと悟り、オスカーをつけ回した理由をあらいざらい白状した。
「何だと? そんなつまらない理由で、この俺を不名誉な噂の主にしたっていうのか、お前は」
オスカーは呆れて果てた声でランディに言った。
「俺にとっては大事なことなんです!!」
次に訪れるはずの幸福な恋の成就を切望するランディは必死である。
「男は他にもいるだろう。下着屋のリュミエールを見ろ。人畜無害な顔をしてはいるが、客といちゃついてばかりいるじゃないか。客もまんざらじゃないみたいだしな。アイツのほうがよっぽど質の悪い男だと、俺は思うぜ」
「オスカーさんじゃないと駄目なんです。僕とつき合っていた女の子はみんな、オスカーさんの店に通うようになるんですから。それにスモルニィ女学院の女の子たちが言ってました。オスカーさんみたいに悪い男の人に憧れるって。だから俺、オスカーさんを見習って悪い人になろうと考えたんです」
オスカーは目眩がした。彼はランディのことを人を疑うことを知らない、元気で単純な奴だとは思ってはいた。しかし、人の言葉を鵜呑みにして、真に受けて、はた迷惑な行動をとるような大バカ野郎だとは、考えたこともなかった。いや、薄々感じていたかもしれないが、まさか自分の身に災難が降りかかるなんて、想像したこともなかったのだ。そう言えば最近、妙に強い視線を感じることがあった。おそらく自分に思いを寄せる内気な女性のものだろうと思い、いずれ視線の持ち主を探し出して甘い言葉の一つでも囁こうと考えていたのだが、よりによって元気と爽やかさ取り柄の単純バカだったとは……。オスカーは自分の未熟さと、はた迷惑な小僧を腹の底から嫌悪した。
「あの……オスカーさん?」
ためらいがちにかけられたランディの声に我に返ったオスカーは、15センチの身長差を最大限に生かして、心配そうに見つめる少年をねめつけた。
「ランディ……今回は大目に見てやろう。だが俺をつけ回すようなことは即刻、やめるんだな。俺を本気で怒らせるようなことをするんじゃないぜ。いいな、坊や」
低い、凄みの入った声に、オスカーの怒りが臨界点を突破しようとしていることを思い知ったランディは、オスカーの尾行を断念することを約束した。
その後、ことの顛末をかの美女に話したオスカーは身の潔白を証明することができた。しかしその後、ランディの純情さにほだされた、オスカーの店の美しい常連客の何人かがランディの店に移り、ファーストフードショップのお得意様だった女子高生の多くが、オスカーの店に鞍替えした。手練手管を駆使して成熟した美女を口説いていたオスカーも、さすがに蕾のような可憐なお嬢ちゃんたちに手を出すことができず、フラストレーションがたまるばかりの生活が続き、ランディは恋の駆け引きを心得たお姉さまたちにからかわれては、顔を真っ赤にしてドギマギするばかりの毎日が続いている。ランディが憧れの『悪い人』になれる日は、限りなく遠い。
でもランディにはとってもお似合いです。
多分、一生『いい人』のランディは、
結構年上のオネーサマに人気があるのではないかと思ったり。