恋慣れた美女との逢瀬から自宅に戻る途中、オスカーは月明かりに照らされている公園を抜けて、彼の自宅でもある喫茶店に帰ることにした。昼間は親子連れや子どもたちで賑わうその空間も、漆黒の闇に浮かぶ月の下では、同じ場所とは思えないほどのロマンティックな雰囲気をたたえている。
「フッ、夜の公園も悪くはないな。今度のデートはここにするか……」
などと独り言を言いながら歩いているオスカーは、その足先に生じた軽い衝撃に気づいた。そこにはオスカーの手に収まるほどの小さな、皮の手帳が落ちていた。皮の表紙はシンプルながらも優雅さを兼ね備えた細工が施してある。その丁寧な仕上がりから、手作りの品だと容易に推測される。彼は持ち主の手がかりはないかと、手帳を広げてみた。一般に『丸文字』と呼ばれる丸みのある読みやすい筆跡は、持ち主の明るく人なつっこい性格を現すに充分だった。スケジュールの欄には誰かとの約束が記されていて、おそらく親しい友人が書き込んだと思われる、色々なマークやサインがカラフルなカラーインクで踊っている。アドレス欄には大勢の友人の名前と電話番号が記入されているが、男女の割合はほぼ同等となっていることから考えると、比較的社交的な性格なのだろう。メモ欄には香りの良い、小さな押し花がいくつか、栞替わりに添えられていた。
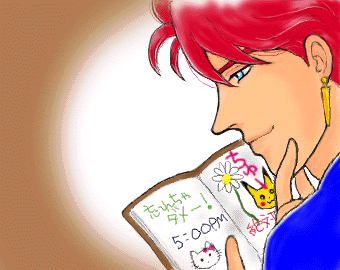
「可憐な花の栞か……。この手帳はまるで炎のオスカー様に拾われるために、ここにあるかのようじゃないか。可愛らしい字の感じでは、まだ10代というところか。手帳の持ち主はきっと困っているだろうな。……12時か。フッ……お姫さまのガラスの靴を見つけた気分だぜ」
オスカーは大切そうに手帳を上着の内ポケットに入れると、上機嫌で足早に帰り道を急いだ。
夜の公園で拾った手帳を、リビングの明るい照明の下で見ていたオスカーは、持ち主への手がかりとなりそうなものを何一つとして見つけられなかった。
「このお嬢ちゃんときたら、ずいぶんとドジだな。友達の名前やアドレスはこんなにきちんと書いているのに、自分のことは何も書いてないなんてな。いや、このお嬢ちゃんはきっと、友達思いの優しい少女なんだろう。少々お人好しで世話好きで……。だから自分のことより、友達のことばかり書いてしまうんだ。それを心配した友達が、いろんな落書きをして……。きっと楽しい学校生活を送っているんだな。幸せそうなお嬢ちゃんの顔が目に浮かぶようだぜ。耳にリボンをつけた白い猫、黄色いネズミ、黒いペンギン……このシールはスモルニィ女学園のお嬢ちゃんたちが持っているのを見たことがあるな。最近流行っているとか言っていた……。フッ、お嬢ちゃんへたどり着くための道しるべを見つけたぜ。待っててくれよ」
一人で盛り上がっているオスカーだった。
その翌日、オスカーは早速、店の常連のスモルニィ女学園の生徒に皮の手帳を見せ、持ち主に心当たりがないかを尋ねたが、良い返事は得られなかった。彼女たちの話では、スモルニィ女学院の生徒の殆どがファンシーショップで売られているビニール性の手帳のカバーに思い思いのイラストや写真を入れ、自分だけの手帳にしているし、こういった皮の表紙のものを使うのは、もっと年齢の高い人だという。店にいた女子大生に手帳をなくして困っている友人がいないかと尋ねてはみたが、誰もが首を横にふるばかり。客の一人がオスカーに言った。
「ずいぶん、その手帳の持ち主にご執心なのね」
少し拗ねた、しかし甘さを含んだ言葉に彼はウインクをしながら答えた。
「当然じゃないか。手帳を落として困っている女性を放ってはおけないだろう?全ての女性が俺にとって大切な存在だからな」
「じゃぁ、私は?」
「当然のことを聞くんじゃないぜ、レディ。君の魅力は誰よりもよく知っているつもりなんだがな。拗ねたそぶりも可愛いが、ずっとそのままじゃ君の美しさが台無しになっちまうぜ」
「じゃあ、明日の夜、私を誘ってくださる?」
「君の魅力的な笑顔にあらがえる男は、世界中、どこを探したっていやしないだろうぜ。」
手帳の持ち主は見つからない時は、デートの相手をちゃっかり獲得する無駄のない男、それがオスカーだった