頭部をすっぽりと覆うフードのついたマント状の上着の裾は足先までの長さがあるため、一歩踏み出すごとに足にまとわりつく。日頃から活動的な服装を好む鋼の守護聖ゼフェルにとって、歩行の妨げとなるようなこの衣服は、この上なく腹立たしいもの以外の何物でもない。そんな感情を逆撫でするかのように、頭上に輝く太陽は容赦なく渇いた大地と彼自身に照りつけている。彼の目に映るのは果てしなく広がる熱い砂の海。強烈な太陽の光を吸収した砂の熱を彼の靴は遮ることもなく、じわじわと、そして確実に彼に自然の脅威を伝えてくる。気の短い鋼の守護聖のイライラは既に臨界点に達し、暴走するきっかけを探していた。
「ゼフェル〜、大丈夫ですか〜」
彼の遥か前方を歩いていた地の守護聖ルヴァは立ち止まり、自らが世話役を引き受けている少年に声をかけた。聖地では読書三昧の日々を送っている地の守護聖は穏やかな性格の持ち主である。おまけに動作もスローモーなので、彼が勉強やお説教のが始まるやいなや、その俊足を発揮して姿をくらますのが常であった。しかし砂漠での歩行については、ゼフェルはルヴァにかなわない。それが腹立たしいばかりでなく、一歩踏み出すごとに砂に沈む足を上げることが、これほど大変だとは考えていなかった少年守護聖は、智恵を司る青年守護聖に悪態をついた。
「俺は平気だ! それよりアンタ、こんなクソ暑い砂漠で、よくそんなに早く歩けるな」
「あ〜、ここは私の生まれた惑星ですからね、慣れてるんですよ。普通の地面なら、あなたのほうが早く歩けるじゃありませんかー」
地の守護聖は笑顔を浮かべながら、ゼフェルが追いつくのを待っていた。その隣にいる眼鏡をかけた青年が口を開いた。
「ゼフェル様の故郷には、こういった環境の場所はなかったのですから、仕方ありません」
弱冠27歳で聖地の王立研究院の主任を務めるエルンストは、普段と変わりなく冷静だ。自分は砂漠の熱気でヒィヒィ言っているというのに、涼しげであるとも言える彼の様子にますます虫の居所が悪くなったゼフェルは、食ってかかるように言い捨てた。
「俺はアンタたちみたいに鈍感じゃねーし、野生児でもねーから、こんな所は性に合わねーんだよ」
「それはお気の毒ですね。お言葉を返すようですが、乾燥地帯の出身ではない私も、ルヴァ様と同じように歩くことができていますが……」
「何だとぉ、それじゃアンタは俺がうすのろだとでも言いてーのかよ!」
怒りが頂点に達した鋼の守護聖はエルンストの胸元をつかみ、乱暴に揺さぶろうとした。ゼフェルの行動形式を把握しているルヴァは、それを素早く遮り、困ったように言った。
「あ〜、いけませんよ、ゼフェル。そんな乱暴な……」
しぶしぶエルンストから離れたゼフェルの様子を観察した地の守護聖は、教え子の消耗した様子を見て小休止を提案した。冷たい水で喉を潤したため、鋼の守護聖も少々落ちつきを取り戻したようだ。先程よりも静かな口調で二人の青年に話しかけた。
「エルンスト、さっきは悪かったな。つい、イライラしちまってよ」
「どうぞ、お気になさらないでください。過度な暑さは多くの人間から冷静な思考を奪うものなのですから」
そこにいるだけで暑気あたりを起こしそうな暑さの中、ルヴァとエルンストは内陸部の乾燥した気候などについて語り合っている。うだるような暑さの中で理路整然とした会話を成立させている二人は、ひょっとすると正常な人間ではないのではないかと、ゼフェルは感じていた。ぼんやりと二人を見つめていた鋼の守護聖は、彼らの指の間にある異様なものに目を奪われた。そこには『水かき』のような膜がある。彼は先刻から身体と心を苛む熱気のせいで幻覚を見たのだと思った。一度目を閉じ、心を落ち着かせてから再び目をやったルヴァとエルンストの手元には、先程見た『水かき』が確かに存在している。何度か瞬きを繰り返しても『水かき』は消えない。余りの驚きにゼフェルは言葉もなく二人の指を凝視していた。鋼の守護聖のただならぬ様子に気づいたルヴァが心配そうに声をかけた。
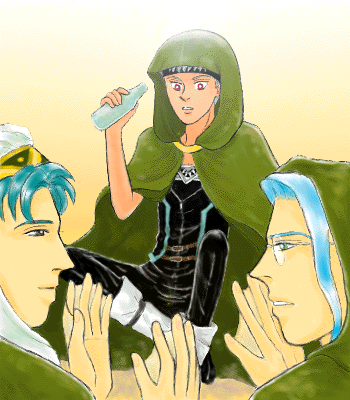
「あの〜、ゼフェル? どうしたんですか? 私たちの手に何かついてますか?」
「……。何って、おめーら、指の間に得体の知れないもんがあるのがわかってねーのかよ」
「異様なもの? 水かきのどこが異様なのですか、ゼフェル様」
いぶかしげにエルンストが少年守護聖に問いかけた。
「そうですよ〜。砂漠に数時間いれば、自然に手足の指と指の間に水かきが生えてくるのは、ごく普通のことですよ。水かきがあるからこそ、足が砂にめり込まずに砂地の上を歩くことができるんです。私はこの講義をあなたにしたこと、ありませんでしたっけ?」
「生まれ育った環境と大きく異なる地域に滞在すれば、そこの環境に応じた進化や変化を遂げるのが自然の摂理です。全ての生物は与えられた、或いは変化する環境に適応するために自らの姿を変えながら生命をつないでいる。人間もまた生物の一種である以上、この運命からは逃れられません。環境に適応できなかった種は、ほどなく絶滅の瞬間を迎えるものなのです」
さも当然のように話すルヴァとエルンストだった。
「ああ、あなたは疲れで少し混乱しているようですね」
心配そうにゼフェルの額に手を伸ばそうとする地の守護聖の手には、肌と同じ色の『水かき』が自分自身の存在を誇示するかのように存在している。鋼の守護聖は彼の理解の範疇を遥かに超えるその物体に本能的な恐怖を覚え、勢い良く払いのけた。その様子を二人の青年は驚いた顔で見つめている。ルヴァはしばし沈黙し、何かを考えているようだったが、少年守護聖をいたわるように声をかけた。
「ゼフェル、あなたは砂漠の旅が初めてですから、少々戸惑っているのかも知れませんが、ほら、あなたの指の間にも水かきが生えてきていますよ〜。今はまだ可愛らしいものですけど、もうしばらくすれば私たちと同じようなものになるはずです」
ゼフェルはおそるおそる自分の手を見た。指の付け根には確かに膜のようなものがある。
「ほら、私は足にも水かきがありますから、裸足でも砂の上を楽に歩けるんですよ〜」
そう言ってルヴァは衣装の裾をめくり上げた。力一杯広げられた足の指の間には手と同じように、皮膚が変化したと思われる膜がある。ゼフェルは慌てて靴を脱ぎ、自分の足の指を凝視した。そこには彼の手と、そして彼の世話役を務める守護聖と同じような膜が存在していた。
「これでゼフェル様も、この先の旅が楽になりますね」
「ええ、本当に良かったですね〜」
二人の青年は心から、ゼフェルの手足の指の間に『水かき』が発生したことを喜んでいるようだ。その嬉しそうな笑顔と反比例するかのようにゼフェルの心は絶望の淵に沈んでいく。
いやだ……俺はバケモンになんかなりたくなんかねーぞ。そうだ、この二人といるから悪いんだ。とっととこの砂漠からおさらばしねーと、マジでこいつらみたいなバケモンになっちまう……。そうだ、逃げるんだ、早く。ここから……。